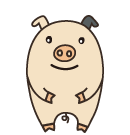小さな国語塾のつぶやき
慣用句の由来
日本語には本当に多くの慣用句があり、何気使っているが実はきちんとした意味や由来を知らないことが多い(少なくとも自分は)例えば「あられもない(姿や態度がだらしなく乱れていること。特に女性についていう。)」という言葉は「あられ(もち米を使ったお菓子)がない状態」と勝手に思っていた。でも、お菓子すらない?なんだか変だなあと言うことで由来を調べてみた。「あられもない」の由来・語源は「そうあってはならない意の『あられぬ』の『ぬ』の代わりに、助詞『も』と形容詞の『ない』がついて一語化したもので、本来の意味は、あり得るはずがない、ありえない、とんでもないこと。」だそうだ。それを知るとふーん成程と納得するのだが、「あられ」を「有られ」と表記したら分かるのに~と内心言い訳をしている。同じような言葉に「台風一過」がある。実は幼い頃にニュースで「台風一過」と聞くたびに、勝手に「台風一家」だと思い込んでいたことも。さすがに、漢字を知ってからは耳で聞いた時に頭の中で「一過」と変換できるようになったが。
2015/09/18 13:39
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です