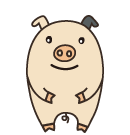小さな国語塾のつぶやき
九重
今日は9月9日、去年のブログで書いたような気がするが・・・9が2回重なることから「重陽の節句」「救急の日」、大分県の九重(くじゅう)地方では「温泉の日」とされている(町内に数多くの温泉が点在し、「九重九湯」と言われることから)。さて「九重」とは中国の王城の門が九重であったということを引いて、もっぱら「宮中」の意味で使われる。宮中と言う意味で使われている代表的な和歌を1つ紹介しよう。伊勢大輔(いせのたいふ/いせのおおすけ)「いにしへの 奈良の都の 八重桜 けふ九重に にほひぬるかな(いにしへの ならのみやこの やへざくら けふここのへに にほひぬるかな)」 【意味】昔みやこのあった奈良の八重桜が、今日は九重の宮中に美しく咲き誇って、一段と輝いていることですよ。「今日」は、「奈良の都」に対しての「京」、「今日」と「京」が掛詞 、一方「九重」は「宮中」と「九回重ねる、幾重にも重ねる」の意が掛けてある。和歌における掛詞や縁語はを見つけるのはなかなか難しいが、折に触れて和歌を鑑賞し古人の思いをはせながら…気付いたら覚えてたとなるのが理想的。

2015/09/09 12:38
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です