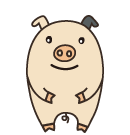小さな国語塾のつぶやき
字の覚え方
中国から渡ってきた漢字をもとにして日本語の「音」に合うように作られたのが「仮名文字」(平安時代)。仮名文字とは「正式ではなく仮のもの」という意味で主に女性が使っていた。当時の子供たちは「天地の詞」=「あめ(天)つち(土)ほし(星)そら(空)やま(山)かは(川)みね(峰)たに(谷)くも(雲)きり(霧)むろ(室)こけ(苔)ひと(人)いぬ(犬)うへ(上)すゑ(末)ゆわ(硫黄)さる(猿)おふせよ(生ふせよ)えのえを(榎の枝を)なれゐて(馴れ居て)」で文字を覚えたという。四八の仮名を重複させずに全部使って作られており、「え」が二度繰り返されるのは当時ア行のエとヤ行のエが音節として区別されていたことを示す。平安後期になると「いろは歌」が広まった。「天地の詞」「いろは歌」ともに詞(ことば)が組み合わされた詩になっているのでイメージがしやすく覚えやすかったと想像する。文法を学ぶにおいては「五十音順」が便利だが、一字一字「あ、あ、あ、・・・」と書いて練習するよりも意味のある言葉として文字を覚える方がスムーズだろう。漢字を覚える時もしかり。最初は書き順などをきちんと確認し、その後は一字ずつひたすら書くのではなく熟語、文章を利用して練習するとよい。
2014/11/02 01:18
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です