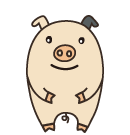小さな国語塾のつぶやき
寇
先日、中学生の授業終了後に中一生徒3人がお互いに「浄土宗は誰?」「法然」「親鸞は?」などなどとお互いに問題を出し合っていた。ちょうど学校で鎌倉、室町のあたりを勉強しているようだ。さて、鎌倉幕府がほろんだきっかけとなった「元寇(げんこう)」〈文永11年(1274)と弘安4年(1281)に、元のフビライの軍が日本に攻めてきた事変。蒙古来(もうこらい)。蒙古襲来。 大辞泉 より〉、日明貿易の時に「倭寇(わこう、海賊という意味)」が暗躍したと習うが、その時の「こう」は「寇」という字を用いる。うっかりすると「冠」と間違えそうになるが、要注意。「寇」という字は先の二つの熟語以外ではほとんど目にすることがないが、一体どんな意味があるのかを知らエべてみた。すると「戦いでとらえた敵を廟に連れて来て、元(頭)に攴[ぼく](打つの意味がある)を加えて呪いをかける字」「寇[こう](あだする、かたき)で、敵、外敵の意味がある。大辞泉より」らしい。成程~、やはり「寇」には意味があったんだと納得。次回の授業では「寇」の意味と「冠」と書き間違えないよう、彼らに伝えようと今から楽しみ。
2016/01/25 14:47
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です