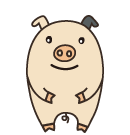小さな国語塾のつぶやき
鍼
「鍼・灸」という看板を時々見かけることがあり、幼い頃はそれを「げん・きゅう」と読み違えており、大分経ってから「はり・きゅう」と読むことを知った。(※「鍼」とは身体の特定の点を刺激するために専用の鍼を生体に刺入または接触する治療法。中国医学のの古典的な理論に基づいている。)「鍼」は当用漢字にないため公的には「はり灸」と表記されるそうだ。なぜ「鍼」を「げん」と読み間違えたか?想像がつくと思うが、「減」の形声文字だと思い込んでいたから。それにしてもなぜ「鍼」と書いて「はり」と読むのか気になったので早速調べてみた。「咸」の音読みは『カン』が『ゲン』、戉(まさかり)で人を脅して口を閉じさせる様子を表す会意文字。漢字の足し算では戉(まさかり)+口=咸(まさかりでショックを与えて口を閉じさせる。)意味は『口を封じる』、『口を閉ざす』となったという。つまり、金(金属)+咸(刺激する)=鍼(金属製の鍼で人体を刺激して治療する。鍼。はり)という会意文字だと知り、長年の謎が解けて何となく誇らしい気分?!突然「鍼」の漢字を取り上げたのには理由がある。先日、友人とのメールのやり取りの中で、友人が高校生の頃に諸所の事情から鍼治療をしたことがあることを知った矢先に1月23日付の十勝毎日新聞で「お灸カフェ」の紹介があったから。幸い、自分自身は現在、体の不調を抱えているわけではないので鍼灸にお世話になることはないが、今後チャンスがあったら試してみるのもいいかも?と思っている。
2016/01/24 05:49
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です