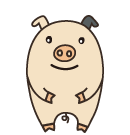小さな国語塾のつぶやき
漢文の決まり
古典と言えば漢文と古文。指導者、中学生共に「漢文と古文だったら、漢文の方が簡単」という意見の方が圧倒的に多いだろう。かくいう自分自身が中学生時代も同じことを感じており、現在もその考えは変わっていない。なぜ漢文の方が簡単かというと暗記するべきことが少ないから、最低限の決まりさえ覚えれば普通の現代文と同じように解けるから。が、ここで落とし穴が。最低限の決まり(返り点、書き下し文にする際には送り仮名はひらがな書きにする、など)以外でも覚えておきたいことが二つ。①「不(ず、ざ)」「也(なり)」「耳(のみ)」という助動詞、助詞はひらがな書きにすること②「而」「於」といった置き字は書かないという二点。この二点はわざわざ覚えなくても、問に注釈として「『不』はひらがな書きにすること。『而』は書かない」と載っているが、本文の傍線部を書き下し文にしようと必死になっているうちに、いつのまにか注釈の内容が頭からすっぽりと抜けてしまうもの。それゆえに、注釈があるなしにかかわらず、最初から先の2点は決まり事として頭に入れておいたほうが無難。自分の記憶に基づいて書き下し文にしつつ、さらには注釈で確認すると言った具合に。実際に昨日の中学生クラスで注釈に色を付けて目立たせた上に、二点の決まりを紹介した後に演習を行ったが・・・初めて取り組む漢文だったため一年生はうっかりミスが相次いだ。結局は頭で理解したことを実践して自分のものにすることが大切。
2016/01/23 03:15
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です