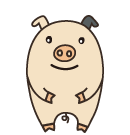小さな国語塾のつぶやき
かぶく者
ちょうど去年の今頃、生まれて初めて生の歌舞伎を楽しんだ。以来、すっかりはまってしまい、必ずまた観劇に行こうと張り切っている。さて、「歌舞伎」の語源は元々「かぶく(傾く)」の連用形「かぶき」が名詞化したもので、「かぶき」に歌・舞・技を当て字にしたという。「かぶく」の「かぶ」は「頭」の古称といわれ、「頭を傾ける」が本来の意味であったが、頭を傾けるような行動という意味から「常識外れ」や「異様な風体」を表すようになった。⇒そこから転じて、人生を斜(しゃ)に構えたような人、身形(みなり)や言動の風変わりな人、アウトロー的な人などを「かぶきもの」と呼んだという。つまり日本の伝統芸能の歌舞伎の元々の語源はあまりいい意味ではなかったということになる。少しショックだが、人と違う才能を持っている人、格好をしている人はどうしても目立つため、特に昔の日本人にとっては異端者として映ったのだろう。でも、たんなる変人なのかそれとも実は天才なのかは明確に線引きすることは出来ず、また時代によって、その時代が求める逸材の中身が違ってくる。もしも人と違った発想、気質を持っているならば、それらをマイナスにとるよりも時代を先取りしている?と発想を少し転換するのも面白いかも?!
2016/01/15 11:34
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です