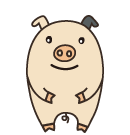小さな国語塾のつぶやき
申
7日までは、まだまだお正月・・・、というわけで今日も「申(さる)」の話題。申とは元々は雷の象形文字、雷は天にある神の威光のあらわれと考えられたので、「神」の字に使われる。また、雷(稲妻)はまっすぐに落ちることから、「紳」(ふとおび。からだをまっすぐのばすおび。転じて、高官が用いる礼装用の太いおび。 地位・教養が備わったりっぱな人。インテリ。知識人。)や「申す」「伸びる」という字に用いられるようになった。では、いったいなぜ「申」が「猿」に?実はこれは単なる当て字。読み方が同じ字を当てただけ。中国を中心とした東アジアの世界では、子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥の十二支を使って暦、時刻、方角を表した。数字でもなんでもない漢字の順番を覚えるの大変なので、神様に新年の挨拶に来た十二種類の動物になぞらえて十二支に宛てて覚えたとか。そんなこんなでたまたま「申」を「さる」と読むことから「猿」が当てられた。🐵には「伸びる」という意味はないけれど、まっすぐに伸びる一年にしたいもの。
2016/01/06 00:12
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です