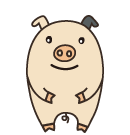小さな国語塾のつぶやき
断腸の思い
今年は申年ということで、ラジオ番組では高崎山自然公園の飼育係の方がゲストで「猿」の生態について語っておられた。人間は猿よりも賢いと思っているため、何かと上から目線で見てしまいがちだが、実は猿から学ぶことが多いという。その代表的なことが「子育て」。猿は子ザルをたっぷりの愛情を込めて育てつつも、厳しくするべき時は厳しく、そしてほどよい距離で子供を見守っているとか。長年、猿の生態を観察している方のコメントはとても説得力がある。さて、「断腸の思い」という故事成語がある。意味は「はらわた(小腸のこと)がちぎれるほどの大変つらい思い」で、由来は「晋(しん)の国の桓温(かんおん)が船に乗って谷を過ぎる時に、その家臣が猿の子どもを捕まえた。母親の猿が子どもを追って百里あまりもついてきたが、家臣は子どもを殺してしまった。これを見た母親の猿は泣きさけんで死んでしまった。その腹をさいてみると、腸がちぎれていたことから、この語ができたという。猿の母の愛情の深さ、さらには腸がいかに動物の精神とつながっているかを物語っている故事成語だと言える。それにしても、3~4世紀に猿の生態、腸の大切さを既に知っていたと思われる中国文明・・・・侮ること勿れ。
2016/01/05 00:28
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です